現代へのアンチテーゼ - 恬淡、颯爽とした「風の男」 -
「葬式無用、戒名不用」。白洲次郎がのこした、たった二行の遺言らしき書付だという。(新潮文庫『プリンシプルのない日本』のあとがきの中で、詩人の辻井喬が述べている)。
戦後、吉田茂らとともにGHQとわたりあって新憲法を制定し、サンフランシスコ講和条約を取りまとめた白洲次郎は、1902年、兵庫県芦屋の素封家に生まれた。
旧制の神戸一中から英国ケンブリッジに留学。時に17歳。180センチを超える長身と日本人離れした甘いマスクで、彼の地でも気後れすることなく、ベントレーやブガッティーを乗り回すなど、絵に描いたような貴族スタイルの青春を謳歌する。
が、その生活も長くは続かず、実家の倒産(1928年)に伴い、帰国。翌年、樺山伯爵家の次女、正子と結婚。英字新聞社や英国資本の商社勤務を経て、一時期「日本水産」の取締役を務めていたというから、今の金子原二郎長崎県知事の先輩でもある。
筆者が白洲次郎に興味をもったきっかけは、皮肉にも「村上ファンド事件」からだった。何が〃皮肉〃なのか?それは、同ファンドの代表者である村上世彰が、白洲が創設した通商産業省(今の経済産業省)の出身者だったからだ。しかも、同じ関西人。
人間は「見た目で判断すべきでない」という教えもあるが、どう見てもこの二人は〃対極〃だ。白洲が恬淡、颯爽とした「風の男」であるのに対し、村上は眼だけがギラギラとした「拝金主義者」。もっとも比べること自体が無意味ではあるが…。
白洲はお坊ちゃま育ちではあったが、一本、筋の通った「男」であった。だからこそ、24歳も年上の大宰相の〃懐刀〃として、戦後日本発展の礎を築くことができたのである。
最近ではNHKがドキュメンタリー番組を制作したり、次々と「白洲本」が刊行されるなど、ちょっとした〃ブーム〃の感もするが、効率一辺倒主義の現代の風潮に対するアンチテーゼなのは間違いない。
講談社版、北康利著『白洲次郎 占領を背負った男』を読むと、その人となりが良くうかかがえる。誰が相手でも物怖じせず、堂々と持論を展開した。
憲法制定に当たってはGHQ当局と激しく対峙。東北電力会長時代には斯界の第一人者、松永安左衛門(壱岐出身、「電力の鬼」として畏れられた)と丁々発止の駆け引き勝負。
一方で、学生運動にも一定の理解を示し、田舎に「庵」を構え畑仕事にも汗を流した。こうしたエピソードを知るにつけ「〃大〃胆な〃和〃解で大和魂を!!」などと、下手なダジャレで郵政造反議員の復党を呼びかける前自民党幹事長の姿が、益々カッコ悪く見えてしまうのである。
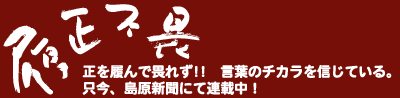






0 Comments:
コメントを投稿
<< Home