母の和製英語に〃脱帽〃 - 「おはぎ」を英語で表現すると -
「極右と極左の思想は紙一重」などと言われるが、「新しいモノと古いモノ」の間にも相当近いものがあるような気がする。
我が家の母は昭和6年生まれの典型的な戦中派で、女学校時代は通学の途中で敵国アメリカの「星条旗」を踏み付けることを日課としていた、という。
であるから、当然の帰結として「英語は苦手」である。ところが時々、何ともユーモラスな〃和製英語〃を披露してくれる。
5日付の行事欄を見ると、有明町で「第1回島原市農業感謝祭」、諏訪の池ビジターセンターで「名月鑑賞会」といった日程が組まれているが、要は「月見の宴」である。
さて「月見」と言えば、ススキに団子といったところが定番だが、この季節、お彼岸の「おはぎ」も捨て難い存在だ。その「おはぎ」を我が母は「ナカメシ・グルリアン」と英訳される。初めて聞いた時は、可笑しさの余り吹き出してしまったが、まさに〃言い得て妙〃である。
母の手にかかると、ジャック&ベッティもトム&スージーも恐らく顔色を失くすだろう。靴は「ハクト・へール」、饅頭は「オスト・アンデル」。さらに「兄やんなボーイ、姉しゃんなガール」などと続く。
そのせいかどうか知らないが、金子助役のことを「キンコスケヤク」と読む三男坊は、学校英語の成績はさておくとして、祖母仕込みの〃島原スラング〃は大得意のようである。
でも、よくよく考えてみると、「おはぎ」を英訳しようとしても、関係代名詞等を駆使して説明するしかないのだから、「SABO」(砂防)や「KOBAN」(交番)のように、「ナカメシ・グルリアン」を〃世界共通語〃として売り出した方がより合理的なのでは?
ところで、プロゴルファーの宮里藍(沖縄出身)がこのところ好調だ。米国ツアーから帰国後はたちまち二連勝。先週の日本女子オープンでも堂々三位に入賞した。
筆者もテレビで観戦していたが、最終組で一緒に回った韓国の張晶に敗れた後も、少しも悪びれることなく「コングラチュレーション」と言って、勝利を称える姿は清々しかった。
実は、宮里らの活躍の陰には地域挙げての支援体制がある、という。沖縄と言えば、小渕恵三元首相が学生時代から通いつめた場所で、早大校友会沖縄県支部長を務めている弁護士の小堀啓介さんらが奔走しているおかげである。
小堀さんによれば、中国(特に上海)は大変にゴルフ熱が盛んで、沖縄を手本に練習に励んでいる、という。「プレーだけではない。試合後のコメントも素晴らしいでしょう。彼(女)らはまさに地域の総合力の賜物なのです」。
時に、我が三男坊の島原スラングの訛りはいつ取れるのだろうか。こちらは家庭の総合力か!?
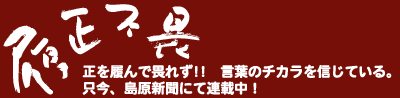






0 Comments:
コメントを投稿
<< Home