安らかな〃旅立ち〃と - 「朝に道を聞かば、夕べには…」 -
私事になるが、我が一族本家(大手)の当主の奥様が21日、亡くなった。まだ満55歳の若さである。「残念」の一言だ。
元気な頃は恰幅に恵まれた陽気なママさんだった。とりわけ、小生とは辛らつな〃批判&批評〃をぶつけ合う間柄で、好敵手的存在だった。
闘病6年。ご主人をはじめ家族挙げての必死の看護も、「ガン」という〃病魔〃を打ち負かすまでには至らなかった。
遺族によると、静かな旅立ちだった、という。連絡の電話が入ったちょうどその頃、小生はある本を拾い読みしていた。
題名は『おじさんはなぜ時代小説が好きか』。関川夏央著。岩波書店から出ている新刊本で、山本周五郎や吉川英治、司馬遼太郎らを取り上げている。たまたまではあるが、藤沢周平の章を開いていた時に、訃報のベルが鳴った。
藤沢(故人)と言えば、最近人気の作家で、先年は木村拓哉主演の『武士の一分』が映画化され、評判を呼んだ。
著者によると、藤沢が「心に残る作品」の一つとしてハンス・カロッサの『ルーマニヤ日記』を取り上げている。同作品は〃死の風景〃にあふれた実録的小説だという。
【軍医だったカロッサが白樺の幹の間に倒れていたルーマニア兵のかたわらを行き過ぎようとした時、死んでいると思われた兵隊が外套の裾を引いた】
【カロッサが(意を決して)モルヒネの注射を打つと、その兵隊は白樺の幹に頭をもたせかけ、気持ちよさそうに両眼を閉じた。そして、その眼窩に大きな雪片が落ちてきた】
藤沢自身、若い頃から当時「不治の病」と言われた結核にかかり、長い間療養生活を送っている。著者はその状況を「生と死のインターフェイスのようなもの」と表現している。
小説の世界に限らず、我々が現実生きている世界も「生」と「死」は常に隣り合わせだ。こうしている間にも、多くの命が生まれ、そして多くの人々が死んで行く…。
古人は「朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり」と悟りに近い言葉を遺しているが、小生の如き凡人にとっては、「死」はひたすら悲しく忌むべきものだ。
先般、三男の卒業式に家人とともに出席したが、式辞に立った校長がこう力を込めた。「自ら命を絶つようなことは断じてなりません」と。
その言葉を聞きながら、もう随分と以前、夏休み前の児童達に心構えを説く、ある小学校長の話を思い出した。「皆さん二学期には、生きたままの姿でまたここで会いましょう」。今にして思うに何とも〃含蓄〃あふれる言葉でないか。
身近な人の「死」に接して様々な思いがよぎる。〃死に顔〃は安らかだった。カロッサではないが、最期は苦しまれずに旅立たれたことだと想う。合掌。
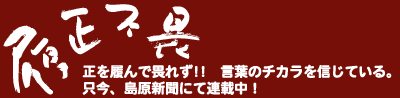






0 Comments:
コメントを投稿
<< Home